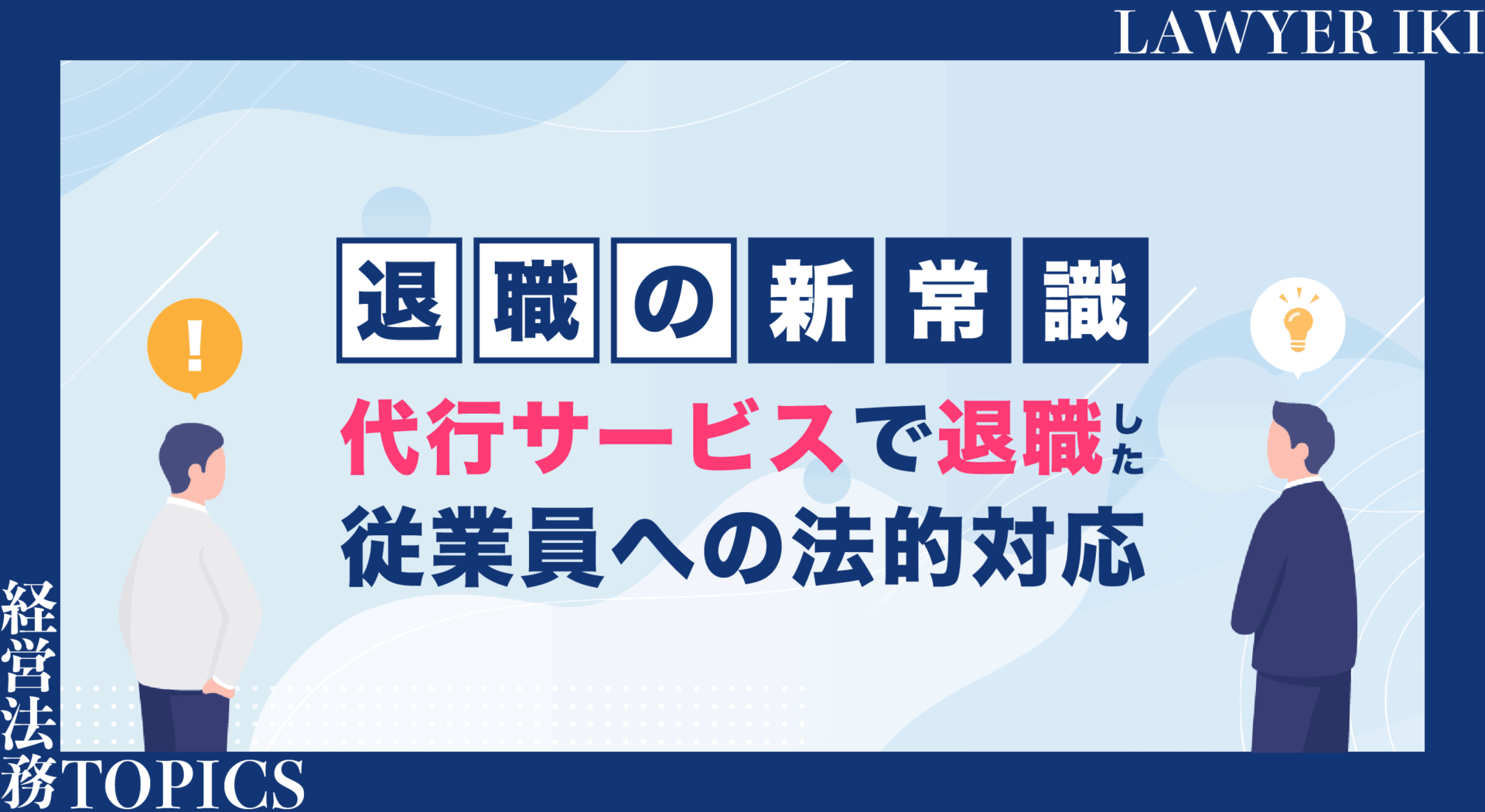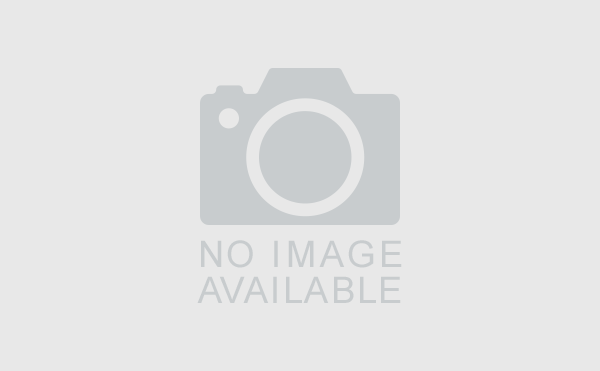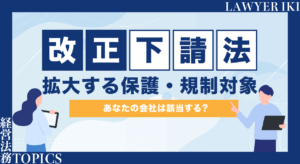経営法務ニュースVol.47|2025.05
坪3.2万円のオフィス
天神ビッグバンの代表的な施設である、ワン・フクオカ・ビルディング。
先月24日に開業しましたが、機会があり、開業に先立ってオフィスフロアを見ることができました。
ただ、オフィスフロアの最上階17階はまだテナントが入居しておらず、展望フロアみたいになってしまっていました‥
坪3.2万円からの眺めはなかなかのものでした。

移転先を探されている方はご検討ください。(私は何の関係者でもありません。)
今回の記事
- 経営法務TOPICS
- 退職の新常識-代行サービスで退職した従業員への法的対応
- 退職代行サービスができること
- 退職代行を利用された際に企業ができることとは?本人への直接確認できる?
- 労働組合型退職代行への注意点
はじめに
近年、「退職代行サービス」を利用して退職する従業員が増加しています。
4月に入社した社員が5月に退社する・・そんな話もあるかもしれません。
従業員が直接上司に退職の意思を伝えることなく、第三者のサービスを通じて退職の申し出を行うこの方法は、労使関係に新たな課題をもたらしています。
今回は、退職代行サービスの概要、法的位置づけ、そして企業としての適切な対応策について解説します。
退職代行サービスとは
退職代行サービスとは、退職を希望する労働者に代わって、退職の意思表示を雇用主に伝えるサービスです。
主に「もう出社せずに辞めたい」「退職を切り出せない」「上司との面談や引き止めが精神的に辛い」といった理由で利用されているといいます。
料金は2〜5万円程度が一般的で、弁護士が運営するものから、一般企業が提供するものまで様々です。
退職代行の法的位置づけ
民法上、労働者は原則として自由に退職することができます(民法第627条第1項)。
期間の定めのない雇用契約の場合、労働者は2週間前に申し出れば退職できます。
したがって、退職の意思表示は第三者を通じて行うことも法的に可能です。
就業規則などで、1か月前の申し出を規定していること、誓約書で引き継ぎの義務などを定めていることなどもありますが、2週間に申し出ると退職できてしまいます。
まず、原則として弁護士以外が運営する退職代行サービスでは、退職の意思表示以外の法律行為(退職金請求、有給休暇取得など)を代理することはできません。
つまり、退職代行は退職することを伝えるだけで、交渉はできません。
弁護士法という法律で、法律交渉ができるのは弁護士だけというルールが決められています。
企業側の対応
まず、私の意見ですが、基本的に退職代行を使って辞めてくる従業員に対しては、粛々と対応するのが良いと考えています。
退職を認めないと伝えたり、直接連絡して交渉をしても会社として最終的によい結果にならないことが多いです。
- ①冷静な初期対応
- 退職代行サービスからの連絡を受けた際は、まず冷静に対応することが重要です。
感情的な反応は問題をこじらせる可能性があります。
退職の意思表示自体は法的に有効であることが原則です。
- ②本人確認
- そもそも退職代行サービスを名乗る連絡が実際に従業員本人の意思に基づくものかは確認が必要です。
本人の個人情報(生年月日、社員番号など)で確認するか、場合によっては本人との直接の連絡を試みることも考えられます。
- ③必要書類と手続きの明確化
- これは、法的な問題というより実務的な問題ですが、退職に必要な書類や手続きについて、退職代行サービスに伝えることになります。
- 退職届の提出方法(書面での提出を求めるか)
- 会社所有物の返却方法
- 退職金や未払い給与の振込先確認方法
- 健康保険や年金の手続きに必要な書類
要注意!労働組合型退職代行ケース
基本的に、弁護士ではない民間企業の退職代行のケースにおいて、退職代行業者としては交渉ができない関係で、本人に連絡をすることも、退職以外の問題について本人との交渉をすることは可能です。
そのため、残業代の請求などをされたとしても、代行業者は交渉できません。
ただし、最近は弁護士ではなくても、代行業者が労働組合を名乗って連絡してくるケースがあります。
その場合、労働組合はいわゆる「団体交渉」として交渉することが可能になるため、実際に労働組合としての要件を満たすケースかどうかの検討することになります。
おわりに
退職代行サービスの増加は、現代の労働環境における新たな課題です。
企業としては、この現象を単に「マナーの問題」と捉えるのではなく、自社の職場環境や組織文化を見直す機会と捉えることもできると思います。
なお、退職時に有給が最大限(未消化が多いところは40日など、、)ある場合には、退職の意思表示と同時に、出社しなくなるケースも多くあります。
その場合に「引き継ぎなどを求めたいために、有給を認めないことなどを主張したい」といった相談を受けることもあります。
ただ、有給休暇の時季変更権(労働基準法第39条第5項)は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り行使できるものであり、単に引き継ぎのためだけでは認められないケースが多いです。
また、労働基準法では会社の都合による有給休暇の買取は原則として認められていません。
結果、現実的な対応策は「日頃から計画的な有給休暇の取得を促進し、突然の退職時に大量の未消化有給が残らないよう配慮する」ことが重要になります。