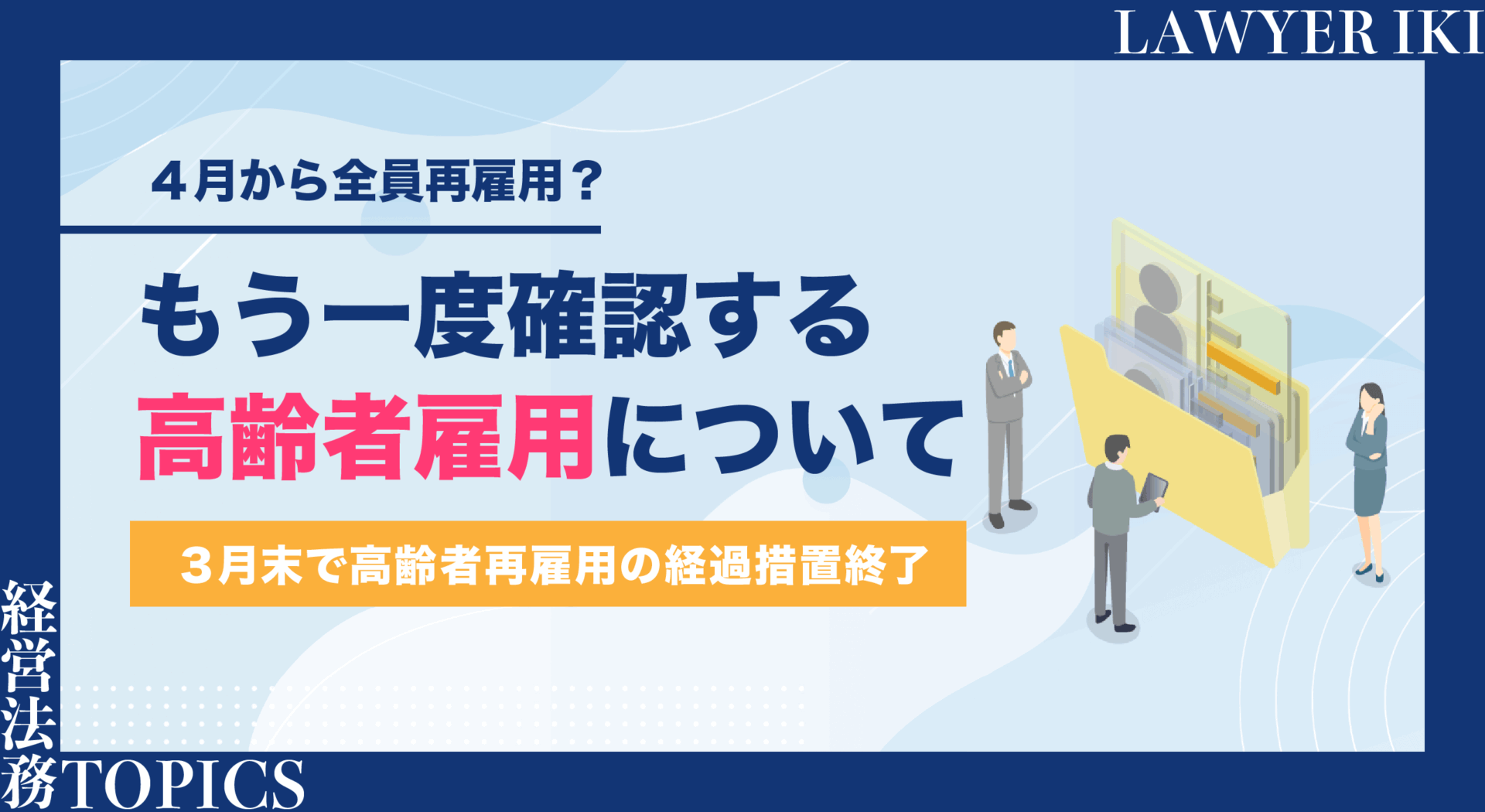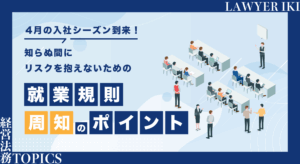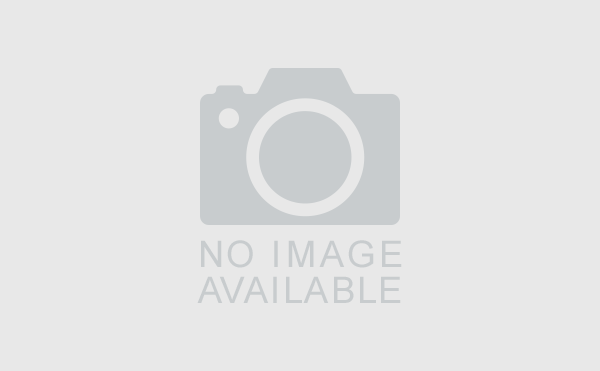経営法務ニュースVol.46|2025.04
担当事件が「判例百選」に掲載されました
「判例百選」と言われても、ご存じない方が多いと思われますが、各法律分野で、これまでの全ての裁判例のうち、重要な100件を厳選してまとめている法律雑誌です。
民法判例百選、憲法判例百選・・・などがあり、弁護士のみならず法律関係者なら誰でも知っている雑誌です。
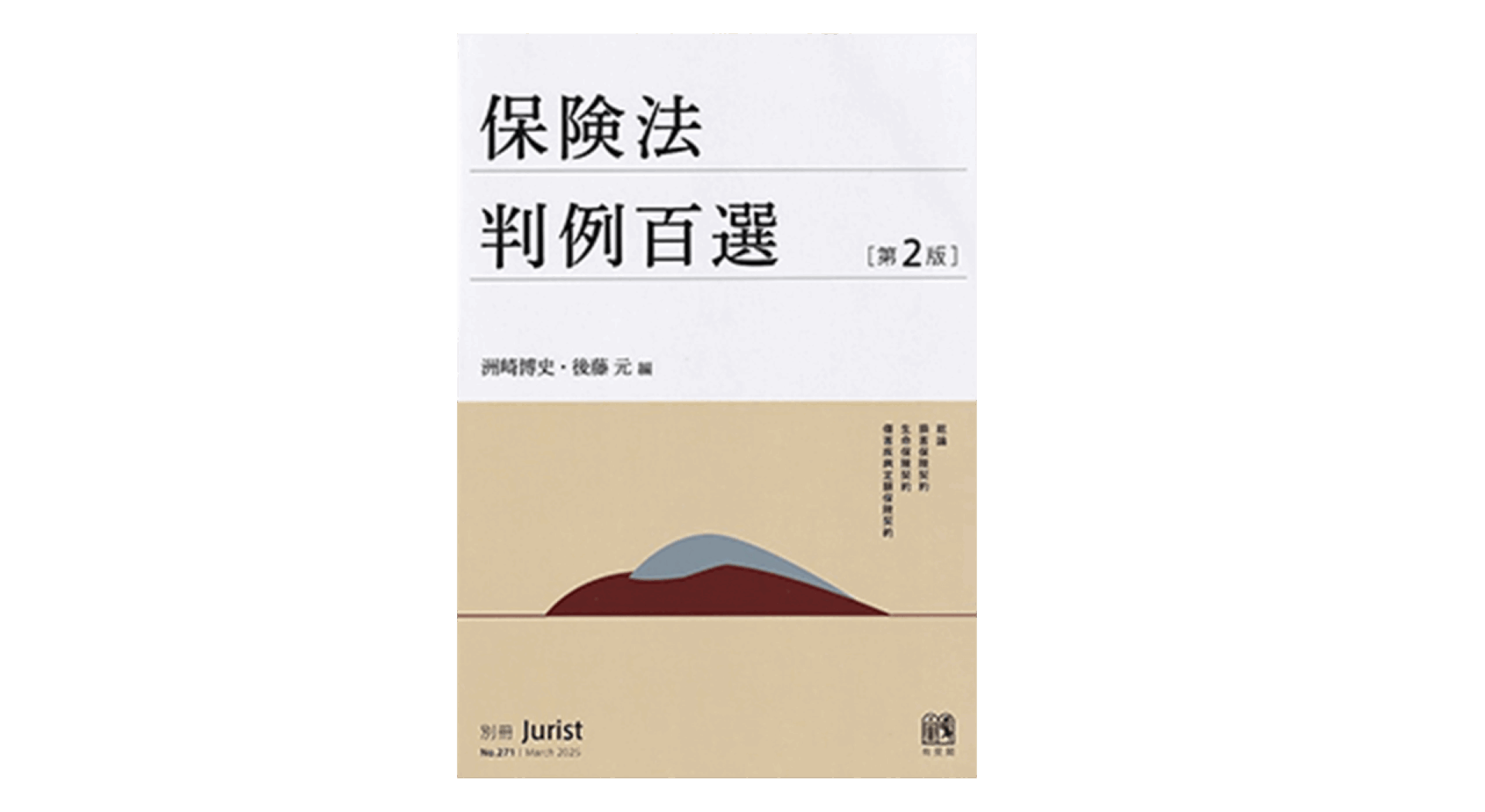
株式会社有斐閣HP(https://www.yuhikaku.co.jp/books/series_search/160)より引用
先日、その判例百選シリーズの中の「保険法判例百選」の第2版が刊行されましたが、その中に私が担当した事件(最高裁第一小法廷令和4年3月24日判決)が掲載されました。
弁護士になる前は自分が担当した事件が判例百選に掲載されるなんてことは考えてもみませんでした。
弁護士としては、最高裁判例を取ることや、裁判例が雑誌に掲載されることを目指すのではなく、依頼者にとって最善の利益を追求する活動をするのが前提です。
ただ、その活動の中で、これまでの慣例や裁判例などの判断を安易に踏襲することなく、依頼者のために新しい判断を求めて戦うことも重要だと再確認しました。
今回の記事
- 経営法務TOPICS
- 3月末で高齢者再雇用の経過措置終了―4月から全員再雇用?もう一度確認する高齢者雇用について
- 3月末で、継続雇用制度の対象者の限定を認める措置が終了
- 4月からは原則として希望者全員の再雇用が必要
- 再雇用時の労働条件の注意点
はじめに
- 定年は60歳まで
- そこからは再雇用で嘱託社員として採用
- 給与は●割減
というのが、中小企業によくある高齢者雇用についての一般的なルールかと思います。
これは、高齢者雇用安定法という法律において、企業には、
- ①定年制の廃止
- ②65歳までの定年の引き上げ
- ③65歳までの継続雇用制度の導入
のいずれかが義務付けられており(令和3年改正で、②③については努力義務で70歳までとなっています。)、③の方法が最も選択されているためです。
令和2年厚労省の調査結果では、75%が③を採用しています。
2025年4月からは
2024年3月末までは、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられることを勘案し、経過措置として、継続雇用制度の対象者を、当該支給開始年齢以上の者について限定することが認められていました。
就業規則でよく見る以下のような基準・表です。
第◯条 従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者であって、高年齢者雇用安定法一部改正法附則第3項に基づきなお効力を有するとされる改正前の高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定の定めるところにより、次の各号に掲げる基準(以下、「基準」という。)のいずれにも該当する者については、65歳まで継続雇用し、基準のいずれかを満たさない者については、基準の適用年齢まで継続雇用する。
- (1)引き続き勤務することを希望している者
- (2)過去◯年間の出勤率が◯%以上の者
- (3)直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
- (4)◯◯◯◯
2 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる期間における当該基準の適用については、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢以上の物を対象に行うものとする。
| 平成25年4月1日から平成28年3月31日まで | 61歳 |
|---|---|
| 平成28年4月1日から平成31年3月31日まで | 62歳 |
| 平成31年4月1日から平成34年3月31日まで | 63歳 |
| 平成34年4月1日から平成37年3月31日まで | 64歳 |
このため、2025年4月からは、高齢者の定年後再雇用に際して、
- 出勤率
- 成績
などを条件にすることはできず、基本的に希望者全員を再雇用しなくてはなりません。
定年で辞めてもらうには、通常の従業員と同様、普通解雇等の条件に合致する場合に限定されることになります。
高齢者を再雇用する際の条件にルールはある?
では、再雇用時の条件にルールはあるのでしょうか。
高年齢者雇用安定法上は、65歳まで継続的に雇用する制度の導入(継続雇用制度を採用する場合)を義務付けるもので、労働条件についてはそれぞれの会社が判断することとなります。
つまり、1年の有期契約として、都度更新していくという労働条件でもよく、仕事の内容が変わることなどによって給与が減額することなども禁止されるものではありません。
注意が必要なのは、再雇用時の労働条件として、業務内容はほとんど変わらないのに、単純に給与だけが減額するというよくあるパターンです。
令和2年の独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査では、100人未満の従業員数の会社に限れば、47%が「定年前と全く同じ仕事」であるとされています。
これは、正社員と嘱託社員間の「同一労働同一賃金」として、よく問題となります。
嘱託社員になって、正社員のときと同一労働であるにも関わらず、同一賃金ではないことが、同一労働同一賃金違反となるというものです。
裁判所は、単に「退職後再雇用」という点だけで、不合理とは言えないとはしていません。
基本的な職務内容等が同一の場合に不合理とされない基準は、裁判例などから退職前と比較して7割程度が目安などとされますが、同一労働同一賃金については、業務内容のほか、その責任の程度、業務内容・配置の変更範囲なども考慮して、不合理かどうかを判断します。
同じ業務であっても、配置転換がなくなっていることや、責任が小さくなっていることなどの事情を考慮して判断するという意味です。
おわりに
高齢者といっても、まだまだ活躍されている方も多く、人手不足の企業においてはその活用も重要な経営課題となっていると思います。
ただ、問題のある高齢者などの対応の問題がこれまで以上に困難となっている状況もあります。
高齢者雇用に関して不明な点があればご相談ください。