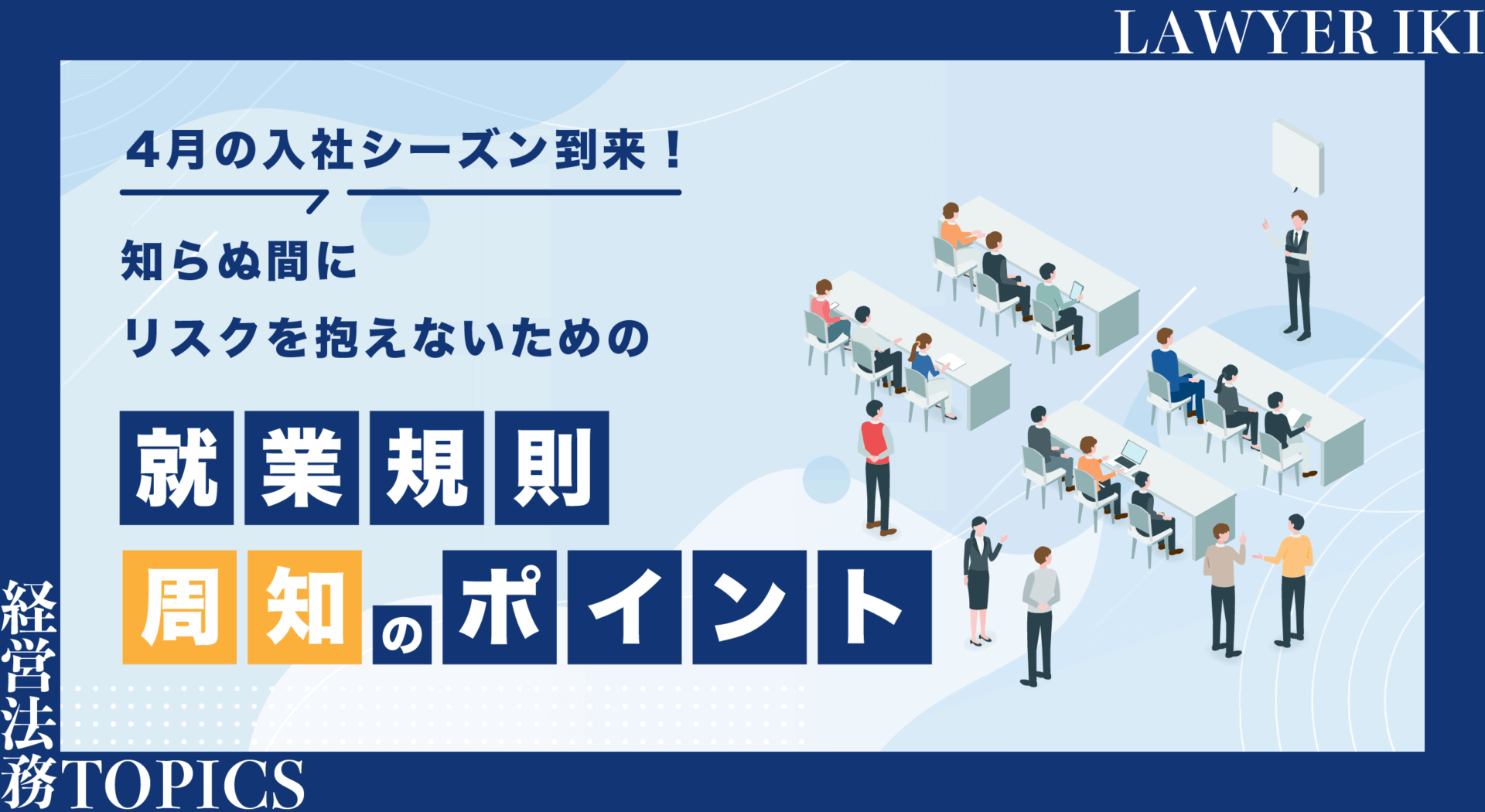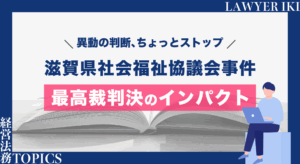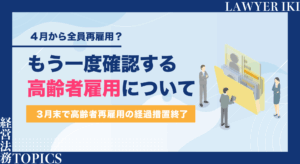経営法務ニュースVol.45|2025.03
ジェスチャー弁護士
最近の裁判は法廷で行われず、WEBで開催されます。
WEB(マイクロソフトのTeams)で、双方の代理人が弁護士事務所から参加して、裁判官だけが裁判所で参加します。
実は意外と接続のトラブルが多いです。例えば、ログインができない、画面が表示されない、などなど。
そういった場合には、電話に変更するなどして対応することになります。
私はこれまで特段のトラブルはなかったのですが、先日の裁判で、なぜか私の音声だけが相手に聞こえないという状況がありました。(裁判所から「壹岐先生の声が聞こえないのですが・・・」と言われて気づきました。)
電話で繋いでもよかったのですが、確認事項が何点かだけだったので、裁判官から「イエスなら「◯」、ノーなら「×」のジェスチャーをしてください!」と言われ、大きく「◯」をして回答して、やり切りました。
和解が成立した期日だったのでよかったですが、相手代理人からは福岡のジェスチャー弁護士などと覚えられてしまったかもしれません。
こんな間抜けな裁判対応は、依頼者には説明できません。
今回の記事
- 経営法務TOPICS
- 4月の入社シーズン到来!知らぬ間にリスクを抱えないための就業規則"周知"のポイント
- 就業規則は会社を守る武器になるが、周知していないと意味がない
- 法律で定める周知方法3つ
- 実際に周知していないと言われるケースとは・・
会社の就業規則はいまどこにありますか?
従業員トラブルで会社を守るための最低限の準備で、就業規則を整備している会社も多いと思います。
しかし、どんなに立派な就業規則を作っていても、それが従業員に周知されていなければ、その就業規則では戦えません。
例えば、とある従業員が問題を起こし、懲戒解雇したあと、その解雇が無効であるとして訴訟になるケースがあります。
その訴訟においては、会社は「就業規則にて懲戒解雇事由に該当するから、解雇処分は有効である」と主張しますが、そもそもその就業規則は鍵のついたロッカーに入っており、周知されていなかったものでした。
その結果、会社の主張は認められず、敗訴する、、
このように、就業規則を準備しておいたつもりでも、その周知ができていないことで、足をすくわれるケースもあります。
周知とは?
労働基準法及び規則では、使用者は、就業規則を
- ①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
- ②書面を交付すること
- ③磁気テープ、磁気ディスク等に記録し、各作業場に従業員が内容を常時確認できる機器に設置すること
で従業員に周知しなければならないとされています(労基法第106条、労働法施工規則第52条の2)。
従業員に就業規則を交付するケースは少ないと思うので、通常は①か③になると思います。
まず、③ですが、要は、「PDFファイルなどを共有フォルダに格納して、従業員であればアクセスできるようにしておく」という対応です。
ただし、「どこに保存しているかを周知する必要がある」ことや、「パソコンを使用しない従業員がいる場合にその従業員が閲覧する方法を容易にしておくこと」などに注意が必要です。
次に①ですが、簡単に言えば、「作業場所や休憩スペース等、従業員が誰でも閲覧できる場所に掲示する」ということです。
特定の従業員しか入れない場所に保管したり、鍵のかかる金庫にしまっておく場合も当然ダメです。
また、社長などの机の後ろの本棚に入れているというのもダメです。普通の従業員は見に行けません。
「従業員から見せてほしいと言われたら見せる」という扱いはどうでしょうか。
法律や行政解釈上明らかではないですが、周知の例として挙げられているものが、従業員がいつでも自由に見ることができるケースであることからすれば、「従業員から見せてほしいと言われたら見せる」という方法は、周知とは言えないと思います。
ちなみに、当然、就業規則を変更した場合には当該変更後の内容を周知させる必要があります。