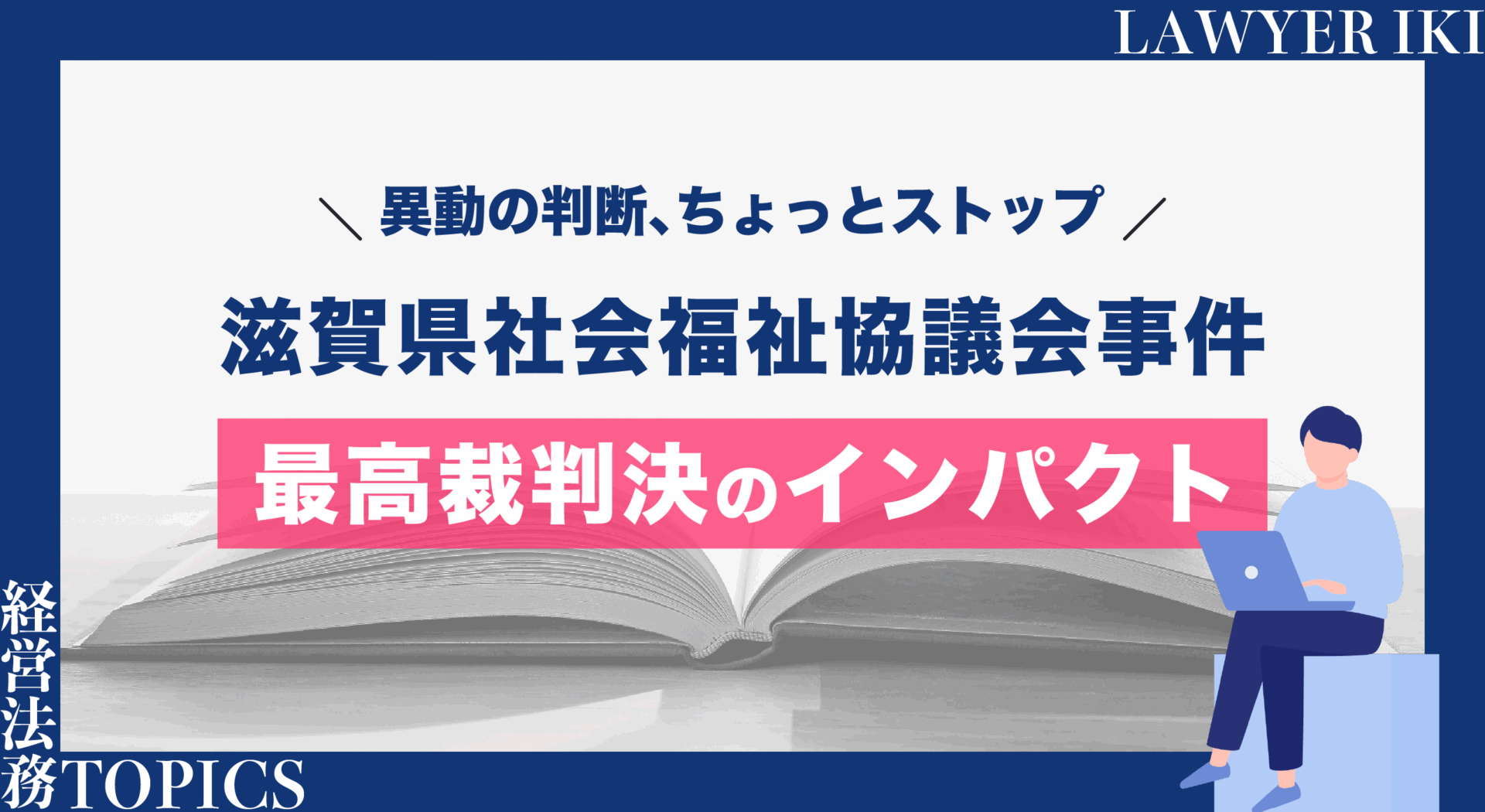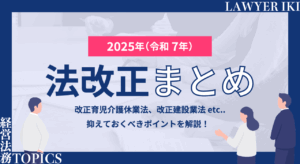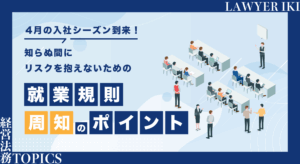経営法務ニュースVol.44|2025.02
雪の降らない北海道?
先日、北海道に旅行に行きました。
旅行の目的は「雪深い場所に行って雪遊びすること」。
絶対積もっているでしょと、目的地を北海道にしました。
しかし実際に訪れると、1月なのにほとんど雪が積もっていない、、
福岡で大雪警報が出た時期と重なったので、なんなら福岡の方が積もっているかも・・という状況でした。
旅館の人に聞くと、「ここは北海道でもあまり積もらない地域でして・・」とのこと
雪遊びはできないけど、温泉でゆっくりするか、、と思っていたら、最終日の前日深夜から、急に降り出し、最終日の朝になんとか目的を達成しました。

おみくじの『【旅行】いずこにてもよし【方角】北東の方よし』が効いてます。
今回の記事
- 経営法務TOPICS
- 異動の判断、ちょっとストップ‐滋賀県社会福祉協議会事件最高裁判決のインパクト‐
- 基本的に「異動」は会社の裁量でできる
- 最高裁判決で職種限定合意がある場合の異動は原則違法に
- 職種限定がある場合で異動させる場合の対応方法には注意が必要
これまで、「配置転換(異動)は会社の人事権の問題であるから、会社の判断でできる。」というのが基本的な考え方でした。
これは、日本の人事労務制度であるパートナーシップ制度において採用されている「解雇はできない代わりに別の仕事をさせることは自由に認める」という考え方です。
しかし、最近よく耳にする「ジョブ型雇用」は、この考え方に大きな影響を与えています。
ジョブ型雇用となると、そのジョブのために採用したわけなので、別の仕事をさせることが難しくなります。
「うちは、ジョブ型なんて関係ない」
なんて思われるかもしれませんが、「ジョブ」というのは特殊な職種ではなくても、職種を限定して採用される従業員には該当する可能性があります。
※法律用語としては「ジョブ型」ではなく、「職種限定合意」といいます。
例えば、Aというジョブで採用したものの、その事業を撤退してA自体がなくなってしまった場合や、ジョブ型で採用した従業員に問題があり、他の仕事に異動させたいといった場合もあると思います。
今回の最高裁判決では、職種限定合意をした従業員を原則として異動させることができないと明言されました。
職種限定合意があるのだから当たり前では??と思われるかもしれませんが、実はこれまでは職種限定合意があっても、雇用維持のために異動を有効とする見解が有力でした。
ちなみに、「職種限定合意」とはどのようなケースで認められるのでしょうか。
例えば「営業」として採用した場合も職種限定となるのでしょうか。
「経理」などで採用した場合はどうでしょうか。
これまでは、病院の医師、看護師など特殊な資格や技能を有する場合や大学教員など専門性が高いとされる場合にのみ、その合意は認められていました。
しかし、昨年の法改正において労働条件の明示ルールが変更になり、職種について将来の変更の可能性についても記載が必要になったこと(将来変更なしと記載されたケース)や、ジョブ型雇用が進むことで、特殊な資格や技能、専門性などまでは一般的に有しないケースでも職種限定の合意があると判断される要素につながる可能性があります。
ちなみに、裁判例で職種限定合意を認めた職業としては、上記の例のほか以下のようなものもあります。
- 調理師
- ゴルフ場のキャディ
- 損害保険募集人
- 採用育成、組織運営に従事する管理職
- 大学職員
職種限定合意がある場合の異動をさせる場合の対応としては、従業員の同意を取るといった対応をするケースが多いと思います。
同意の取り方も、後に争われないように、事前の説明を踏まえて書面での作成が必要となります。
ただし、職種限定合意があるにも関わらずその仕事自体がなくなってしまった場合などには、いわゆる整理解雇などを検討する必要があります。
「ジョブ型なのだから解雇もしやすくなる」が本来の考え方ですが、現時点ではそこまで解雇規制自体が緩和されていないので、いずれにせよ慎重な対応が必要になります。
職種限定合意がある社員の異動に際しては、
- 同意を取って異動させる
- 整理解雇の要件である解雇回避努力として、異動を提案する
- 応じない場合に解雇を検討する
という流れになります。
ちなみに、雇用契約書の書き方によっては意図せず職種を限定しているように読める記載となっていることが多くありますので、雇用契約作成時(採用時)も、異動を検討した時点でも、それぞれ対応に注意が必要です。