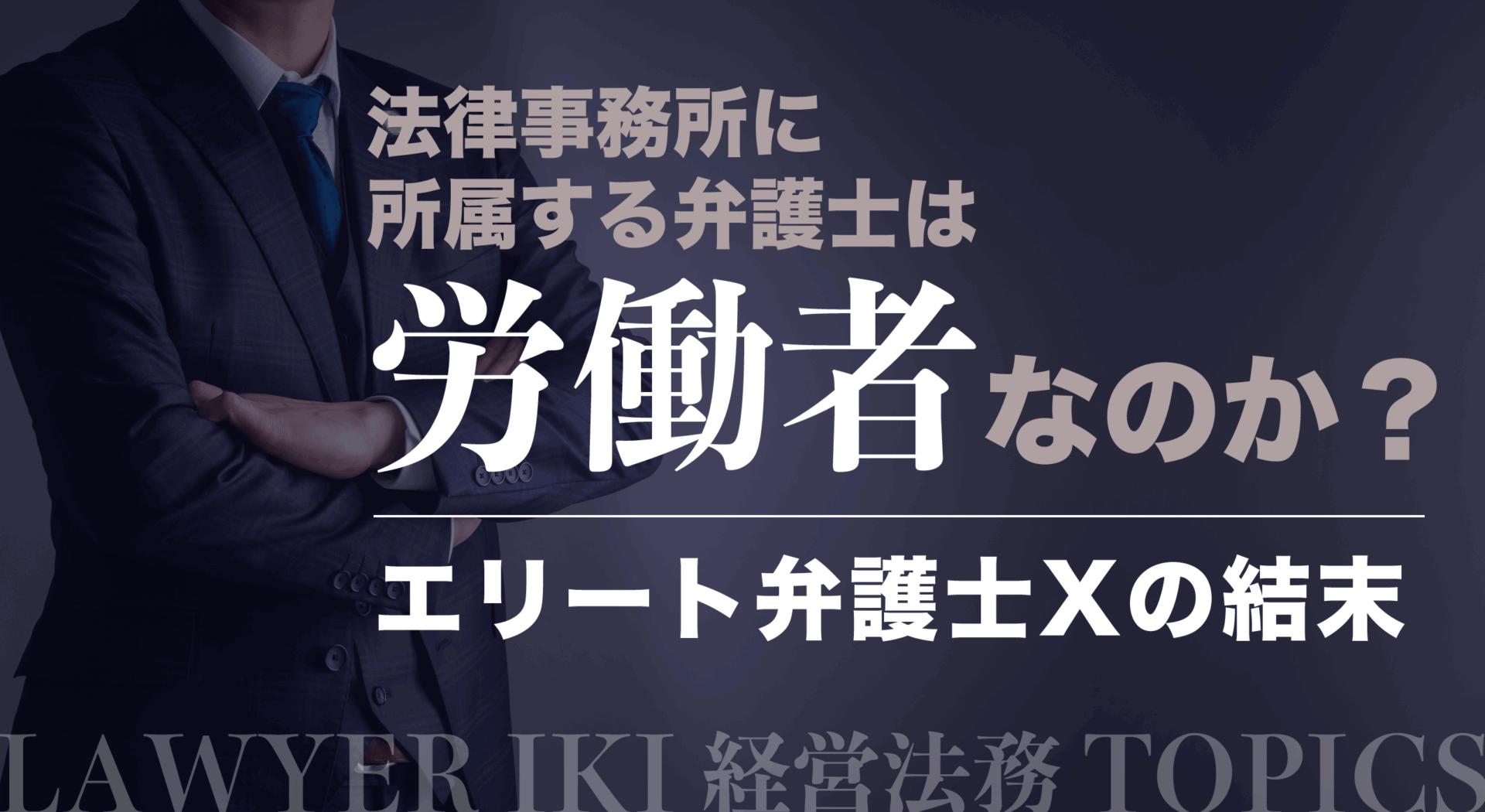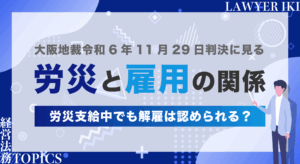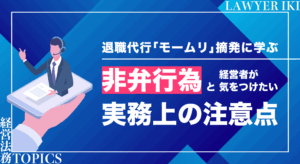経営法務ニュースVol.52|2025.10
駆け込み
皆様、大阪万博は行きましたか?
私は先日日帰りで駆け込んできました。
「万博に行っておかないと次に行く機会はなかなか訪れないのではないか…」などとまんまと乗せられて駆け込みましたが、同じように考えている人が大量にいらっしゃったのか地獄のような人混みでした。
当然パビリオンの抽選も全滅で、予約不要の万博を少しみただけで、疲弊して帰ってきました。
もう今年は列に並びたくないです。

当日の壹岐のイメージ
※関西の皆様お声かけせずに失礼しました。余裕を持ったスケジュールでいずれ行きます。
今回の記事
- 経営法務TOPICS
- 法律事務所に所属する弁護士は労働者なのか?-エリート弁護士Xの結末-
弁護士が所属する法律事務所の中での勤務体系をイメージするのは難しいかもしれません。
いわゆる独立開業している弁護士や、弁護士に雇われている弁護士(アソシエイト、イソ弁)、組織に属しながらも独立採算で活動している弁護士など、弁護士の働き方には、それぞれあります。
今回ご紹介するのは、日本最大の法律事務所である西村あさひ法律事務所で、とある弁護士が、自分は「労働者」であると主張し、労働者としての権利を主張した裁判の判決です。
エリート弁護士、人生を変える転職
この裁判で、原告となった弁護士は、平成13年から弁護士をしている昭和52年生まれの男性でした。
この弁護士を「弁護士X」といいます。
弁護士Xは、弁護士登録をした平成13年から、とある法律事務所に入所し、ファイナンスや税務関係を専門として働いており、銀行を依頼者とする案件を担当していました。
その後、海外のロースルクールに進学し、アメリカでの法律事務所の勤務経験もある、いわゆる渉外系のエリート弁護士です。
そんな中、在籍している法律事務所が特化しようとしてる業務分野と、自身の専門分野がマッチしていないと感じた弁護士Xは転職活動を行います。
その転職希望先が、日本最大の法律事務所である西村あさひ法律事務所でした。
西村あさひ法律事務所は、弁護士数700名を超える日本最大の法律事務所で、国内外の大企業を中心とする企業法務案件を中心に取り扱っています。
弁護士Xは、西村あさひ法律事務所への転職活動において、「私が培ってきた知識や経験の共有を図ることで、チームで一体となってクオリティの高いリーガルサービスを提供できるように貢献したい」とアピールし、平成26年から西村あさひ法律事務所への入所が決まりました。
条件は、
- 年間報酬1800万円+個人業績と事務所業績に応じた特別報酬
- 2年契約で、以後は1年毎に更新
という内容でした。
契約書は、労働(雇用)契約ではなく、「委任契約」とされていました。
その後、弁護士Xは転職前に依頼者であった銀行を西村あさひ法律事務所に紹介するなどして、引き続きファイナンス、税務案件を中心に活動していました。
暗転するキャリア、不測の事態と転落
弁護士Xは、平成29年に自転車で道路を走行中、停車中の自動車のドアに衝突し、外傷性くも膜下出血、脳挫傷等の傷害を負い、一時意識不明の重体となりました。
なんとか意識は取り戻し、3か月後には復職することができました。
しかし、その後事故の影響かは定かではありませんが、依頼者が求めた提出期限までに作業を終えることができず、上司であるパートナー弁護士から進捗状況を管理されるようになります。
また、弁護士Xは、依頼者である銀行との打ち合わせで、その銀行から直接、その仕事ぶりに対して厳しい叱責や抗議を受け、打ち合わせを退席させられ、その後、担当を外されました。
さらに、弁護士Xは上司であるパートナー弁護士から、法律意見書の作成を指示されたものの、期限までに完成できず何度も督促を受けるなどから、徐々に仕事を振られなくなっていきました。
そんな中、西村あさひ法律事務所は、次回の契約更新におて、基準年棒を1500万円とすることを弁護士Xに提示します。
しかし、弁護士Xはこれを拒否し、何度か面談を繰り返しますが、結局折り合いがつかず、最終的に西村あさひ法律事務所は、基準年俸を1300万円とする条件を提示し、これを締結しない場合には、令和4年12月末に事務所を退所してもらう旨を通知します。
これに対し、弁護士Xは、自身は労働者であるため、無期転換権を行使すると伝えます。
有期の労働者は、契約期間が5年間を超えると、期限の定めのない労働契約への転換を申し込むことができます。
これを無期転換権といいます。
弁護士Xは自分が労働者であるとして、これまで通りの基準年俸1800万円での期間の定めのない労働契約を求めました。
しかし、西村あさひ法律事務所は、弁護士Xは労働者には該当しないとしてこれを認めず、弁護士Xは、労働者としての地位を求めて裁判所に訴訟提起しました。
法廷に持ち込まれた「労働者」の問い
裁判所は、弁護士Xの主張を認めませんでした。
理由として、弁護士Xは、弁護士という法律の専門家であり、委任契約に署名押印している事実からして、労働者であるという認識を持っていたとは言えないとしました。
さらに、労働者かどうかの重要なポイントである、事務所からの仕事を断れるか、事務所から指揮監督を受けているかについては、パートナー弁護士からの仕事は断ることもできたし、実際に断ったこともあることや、自身の業務が高度な専門分野であることの認識が有ることなどから自らの裁量で仕事をしていたことなどから、指揮監督を受けていたとは言えないとされました。
また、タイムチャージとしての時間は管理されていたものの、その時間が短くとも、1800万円は支払われていたことなどからも労働者とはいえないと判断されました。
新たな道へ
この裁判は令和7年2月に判決が出されていますが、弁護士Xは、令和5年3月(西村あさひ法律事務所を退職後3か月後)には、別の法律事務所のパートナー(経営者側弁護士)として入所しています。
弁護士Xは労働者と認められるべきだったのでしょうか?
弁護士としての働き方は様々ですし、いわゆる「労働者」として勤務している弁護士も実際にはいると思います。
しかし、一定の経験を持つ弁護士は、自身の裁量をもって上からの指揮監督によらずに仕事をする個人事業主である、というのが弁護士業界の肌感覚であり、今回の裁判所の判決もそれに沿うような内容に思います。